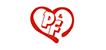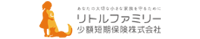小動物に多い
病気やケガは?

身体的特徴
現在日本でペットとして飼われている小動物には、様々な種類があります。
ハムスター、ウサギ、フェレット、インコなど割とメジャーな動物から、モモンガ、クモ、カエル、サソリに至るまで、小動物の種類は実に多様です。
しかしこれらの小動物は犬猫と比較してペットとしての歴史が浅く、野生動物としての生活習慣が抜けていません。
弱肉強食の野生生活では、弱みを見せるのは許されないことです。
そのため小動物は病気になっても症状を隠してしまいがちです。
飼い主が気が付くレベルになった時は、既に重症化した後ということが非常に多いです。
また珍しい動物ほど、対応している動物病院や治療技術を持った獣医師を探すのが難しくなります。
小動物を飼う前に、治療に対応した動物病院があるかどうか確かめておくことをお勧めします。

遺伝性疾患
遺伝性疾患というわけではありませんが、小動物には生まれつきの特徴があり、人間や犬猫と同列に考えると病気リスクを高めてしまうこともあります。
例えば、ウサギの歯は犬猫と違って一生伸び続けます。
通常歯は自然に削れるものですが、餌のやり方や飼育環境によっては歯が伸びてしまい、噛み合わせの異常「不正咬合」がおこることがあります。
不正咬合になると、うまく物が食べられなくなり、食欲が低下したり、よだれや目ヤニが出るなどの症状が現れます。
ウサギは1日食事を摂らないと、すぐに弱ってしまう繊細な動物です。食欲には常に気を配る必要があります。
また体の小さいハムスターは、ちょっとした行動がすぐに事故につながってしまいます。
小動物を飼うときには、動物固有の特徴をよく理解するようにしましょう。
飼育時に気をつける事
ケージ飼いを基本にして、触りすぎないようにする
小動物の多くはケージや水槽で飼うことが基本になります。
ケージや水槽での飼育は閉じ込めているようで、一見かわいそうに思えるかもしれません。
しかし小動物にとって、ケージの外は危険がいっぱいです。
外に逃げてしまい交通事故にあう危険性はもちろん、電気コードをかじって感電するウサギや、飼い主に踏まれて骨折するハムスターもいるのです。
また飼い主にとっては可愛がっているつもりでも、たくさん触られることがペットのストレスになってしまうこともあります。
特に新しく小動物のペットを迎えたときは、スキンシップは控えめに。3~7日は遊ぼうとしない方が無難です。
生活面の注意点
適切な運動量は必要だが、遊びすぎには注意!
ケージで飼っている動物でも適切な運動量は必要です。
例えばハムスターなら、ケージの中に回し車などの運動器具を設置して運動を促します。
ウサギの場合もケージの中に設置できる運動用おもちゃがいろいろあります。
また時々はケージの外に出して遊ばせてあげてもよいでしょう。
ケージの外に出すときは、かじると危険なものを隠し、足を傷めないようコルクマットを敷いたスペースを用意しておくと安心です。
また小動物が危険な目にあわないか、そばで見ていてあげることも大切です。
ただし、遊びすぎには注意してあげてください。
小動物の中の好奇心旺盛な子は、自分の限界以上に遊んでしまう場合があります。
疲れすぎてしまうと抵抗力がなくなり、病気にもかかりやすくなります。
遊びの時間や回数が適切かどうかには常に気を配っておきましょう。
小動物がかかりやすい病気の症状と治療費用をまとめました。
いざというときを考えて、治療費の準備をしておきましょう。
| 病名 | 症状 | 治療費例 |
|---|---|---|
| 毛球症(ウサギ) | 毛づくろいで飲み込んだ毛玉が胃腸に貯まる。 ・食欲低下(全く食事を摂らないことも) ・元気消失 ・便が出なくなる |
・診察料 約1000円 ・入院料 約2,000~3,000円/一日 ・内服薬 約500円 ・注射 約1,500~5,000円 ・血液検査 約300~5000円 ・骨折手術 約8,000~30,000円 |
| 不正咬合(ウサギ、モルモット、チンチラ、テグー) | 歯が伸び続けることで起こる。 ・食欲低下 ・顎骨の変形 ・鼻炎 ・よだれ |
|
| 副腎腫瘍(フェレット) | ・生殖器異常 ・体重減少 ・脱毛 ・貧血 |
|
| 骨折(フェレット、ウサギ、ハムスター、モルモット、鳥、カメなど) | ・歩行異常 ・四肢麻痺 ・排尿困難 ・骨折部の痛み |
幼年期
生まれたての小動物は大変可愛いものですが、かなりデリケートでもあります。
ペットにする時期や触ってもいい時期が訪れるのをある程度待ちましょう。
例えば、生まれたてのハムスターの赤ちゃんに触ることは厳禁です。
母ハムスターは大変気が立っている状態なので、人間のにおいが付いてしまった赤ちゃんには敏感に反応し、時には食べてしまうこともあるのです。
赤ちゃんハムスターを触るのは生後3週間を経過してからにしましょう。
また、生まれたての小動物は健康状態が不安定で飼育が難しいという側面もあります。
小動物を飼い始めるなら離乳の時期を過ぎ、体がしっかりしてきたころを見計らうとよいでしょう。
ウサギなら生後1ヶ月半以上の子をもらうと安心です。
繁殖期
小動物が成体になると、繁殖時期に入ります。
小動物の種類によっては生後数か月で繁殖できるようになるものもありますが、母子の健康状態を考慮するとおおむね生後1年~の繁殖が安全と考えられます。
この頃には生殖器のトラブルによるによるさまざまな疾患も出てきます。
特に家庭で飼われている雌ウサギの場合、性ホルモンの不安定な分泌による疾患が多くなります。
妊娠・出産の機会が野生のウサギに比べて少ないのが原因です。
妊娠していないのに巣作りなどを始める「偽妊娠」に加え、4歳以上になると子宮疾患を発病する可能性が大変高くなります。
性ホルモンによるストレスや生殖器の疾患予防のためには、生後6か月~1年未満の避妊手術がお勧めです。
高齢期
小動物の高齢期は動物の種類によって様々です。高齢期になれば病気の可能性は高くなっていきます。
人間の時間と小動物に流れる時間の違いを認識し、何歳頃から高齢期に入るのかを意識しながら、飼育環境を整えていきましょう。
例えばハムスターは非常に寿命が短い動物で、2~3年でお別れの時がやってきてしまいます。
高齢のハムスターは心臓や呼吸器の病気を発症することが多いです。
これらの病気では呼吸が荒くなったり、体重が減少したりといった症状が現れます。
このような病気は完治が困難なので、薬で進行を遅らせる処置が行われます。
短い命だからこそ、早目に症状に気が付き、苦痛を少しでも減らしてあげてください。
保険選びのポイント
小動物にはいろいろな病気のリスクがあることが分かりました。
病気やケガをしたとき、長引く通院や手術で治療費が高額になった時、補償をしてくれるペット保険の比較ポイントをまとめてみました。
小動物が対象のペット保険を探す
小動物は犬猫といったメジャーなペットに比べて、加入できるペット保険会社の数がどうしても少なくなります。
とはいえ、小動物の治療費を支払い対象にしたペット保険もいくつか存在します。
例えば、アニコムの「どうぶつ健保ふぁみりぃ」は鳥、ウサギ、フェレットを対象にした保険です。
またSBIプリズム少短の「うさぎ等小動物プラン」ではウサギ、モルモット、ハムスター、フェレット、チンチラ、デグー、ハリネズミ、リス、モモンガ、プレーリードッグが対象です。さらに「鳥類、爬虫類プラン」では、オウム、ヨウム、ブンチョウ、サイチョウ、カナリア、インコ、ジュウシマツ、カメ、イグアナを対象にしています。
ただし、小動物の保険に関しては加入できる年齢の上限が犬猫に比べて低いことがあります。
自分のペットが加入できるのか、よく条件を確かめてください。
ペット保険の補償範囲外部分を確認する
ペット保険には補償の対象外となる部分がいくつかあります。
まずは、免責金額です。
免責金額とは飼い主が自分で負担する治療費のことです。
だいたい免責金額が大きい(自己負担が多い)プランほど保険料は安くなりますが、その分保険金が請求できないケースも多いです。
次に、保険の開始期間です。
人間の医療保険と同じく、ペット保険も加入後すぐに補償が開始されるわけではありません。
補償開始前に発症した病気は補償されないことがあります。
最後に、補償外となる病気やケガの範囲です。
予防注射で予防できる疾患や、自然災害によるもの、飼い主の過失や故意によるケガを補償対象外にし、保険金が請求できないようにしている会社は多いです。
中には治療費や発症率が高い病気が補償対象外になっているペット保険もあります。
ペット保険会社やプランを比較する際は補償の内容だけでなく補償外の範囲も確認することが必要です。
アニコム損害保険株式会社
SBIプリズム少額短期保険株式会社
ペットお役立ち情報

ペットライフの役立つペット豆知識・おもしろコンテンツなど、ペットとの毎日が楽しくなるような情報が満載です。
取扱い保険会社・少額短期保険業者一覧