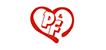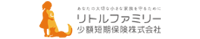大きな体格から「ジェントルジャイアント(穏やかな巨人)」という異名をもつメインクーンは、日本国内でも飼育頭数が多く人気がある品種です。
この記事では、メインクーンが長生きするための健康管理や飼い方について解説します。


大きな体格から「ジェントルジャイアント(穏やかな巨人)」という異名をもつメインクーンは、日本国内でも飼育頭数が多く人気がある品種です。
この記事では、メインクーンが長生きするための健康管理や飼い方について解説します。
メインクーンは性格が穏やかで、広い飼育スペースがあれば飼いやすい猫です。
しかし、その反面肥大型心筋症などの心疾患や関節疾患の好発品種であることが知られています。
まずは、メインクーンの身体的特徴についてご紹介します。
身体的特徴や性格を理解したうえで飼育を行うことで、病気になるリスクを低減することができますよ。
メインクーンのルーツは諸説ありますが、アメリカの北東部にあるメイン州の港町に暮らす土着の猫と、船でやってきた長毛種の交配で誕生したという説が有力です。
「メインクーン」の名前の由来は、もともと住んでいたとされるメイン州とアライグマ(raccoon:ラクーン)を組み合わせたもので、容姿の特徴から猫とアライグマの交雑種であるという伝説からその名がついたといわれています。
メインクーンの身体は、名前の由来となったメイン州の極寒の大自然のなかでも生き抜くために、骨太で筋肉質、がっちりとした体格です。
フサフサした絹の様な被毛は密度が高くて温かく、水を弾きます。
雪の上でも歩きやすいように足裏にタフト(房毛)が豊富に生えていて、耳の先端は尖っていて耳の付近の被毛が多く、耳の先端に飾り毛が生えているのも特徴です。
オスは8~10kg、メスは5.5kg~7kgの大型の長毛種で、メインクーンが完全に成熟するまでには4年くらいかかるといわれています。
メインクーンは、優しく穏やかな性格で、人懐っこい個体が多い猫です。
しかし、温厚だからといって運動量が少ないというわけではなく、無邪気で遊び好きな一面もあります。
性格の面では、初めて猫を飼う方にも飼いやすいと言えるでしょう。
アニコム損害保険(株)が毎年行っている調査では、メインクーンの平均寿命は13歳でした。
同年の猫の平均寿命が14.7歳で、全国的な実態調査の猫の平均寿命15.66歳と比較しても、メインクーンの平均寿命は短いという結果でした。
しかし、各データはあくまでも平均寿命で、何歳まで生きられるかは各個体や生活環境によって異なります。
愛猫が元気で長生きするためには、健康的な食生活とストレスが少ない飼育環境を整えることが最も大切です。
参考:アニコム家庭どうぶつ白書2023 犬と猫の寿命
https://www.anicom-page.com/hakusho/book/pdf/book_202312_2_4.pdf
(一社)ペットフード協会 令和5年(2023) 全国犬猫飼育実態調査
https://petfood.or.jp/data/chart2023/3.pdf
メインクーンの健康管理について、特に重要な以下の3つのポイントについて解説します。
猫は肉食動物で、もともとは小動物を捕食していました。そのため、病気などの理由がない限り、猫には高タンパクの食事が推奨されています。
特にメインクーンは、がっちりとした体格を維持するためにタンパク質が多めの食事がおすすめで、基本的には、総合栄養食(ドライフード・ウエットフード)と新鮮なお水が中心の食事がよいでしょう。
メインクーンは大型種で関節のトラブルが多くみられるため、太らせないようにすることも大切です。
食事の回数は、肥満防止と胃腸を休める時間を作るためにも置きエサではなく、回数と時間を決めて食事を与えるようにすることをおすすめします。
猫のお留守番が多いご家庭では、自動給餌器等を利用するのも有効です。
肥満防止のためには、加工品のおやつや人間の食事は与えない様にする、一日の食事量を量ってその中から与えるなどの食事管理をこころがけましょう。
なお、100%手作り食を与える場合は、リンとカルシウムのバランスや必要なビタミンの不足などが懸念されるので、動物栄養学の専門家から食事について学んでから実践することをおすすめします。
メインクーンは穏やかな性格ではあるものの遊びが大好きで、ある程度の運動量が必要です。
おもちゃで遊ばせる、キャットタワーやキャットウォークなどを設置するなど上手にストレスを解消して運動不足にならない様に工夫しましょう。
猫は、人間よりも早く歳を取ります。
健康的な生活を送るためには、定期的な健康チェックは必須で、最低でも年に1回は血液検査・尿検査などの健康診断を受けましょう。
また、メインクーンに多く見られる肥大型心筋症は、見た目の症状でわからないことも多いため、上記の健康診断と併せて心エコー検査、レントゲン検査、心電図など心臓のチェックをすることをおすすめします。
ワクチン接種と、ノミ等の寄生虫予防について解説します。
子猫はおよそ生後2ヶ月を境に母猫からの移行抗体が減っていきます。
そのため、生後2ヶ月以上の子猫の時期に約1ヶ月間隔で2回のワクチン接種が推奨されています。その後は、1年に1回のワクチン接種を行う場合が一般的です。
なお、WSAVA(世界小動物獣医師会;WorldSmall Animal Veterinary Association)のワクチネーションガイドラインでは、定期的にペットホテルを利用する猫や多頭飼育や室内と屋外を行き来する猫は1年に1回のワクチン接種が必要であるが、コアワクチン(猫伝染性鼻気管炎・カリシウイルス感染症・猫汎白血球減少症)は3年に1回、ノンコアワクチン(上記3つ以外の猫白血病ウイルス・猫免疫不全ウイルス・クラミジア感染症など)は地理的要因や環境、ライフスタイルによって、感染症のリスクが生じる動物にのみ必要だという記載があります。
このガイドラインを受けて、ワクチン接種のプログラムについては各病院によって対応が分かれるというのが正直なところです。
なお、参考までにわたしも完全室内飼いで猫を飼っていますが、動物病院勤務で色々な状況のペットの診察をするため、年に1回3種混合ワクチン(上記でいうところのコアワクチンにあたります)を接種しています。
参考:世界小動物獣医師会 犬と猫のワクチネーションガイドライン
https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/01/WSAVA-vaccination-guidelines-2015-Japanese.pdf
ノミやマダニ等の予防は、完全室内飼育であっても定期的に行うことをおすすめします。
完全室内飼いの長毛種の猫にノミがついてしまい、暖かい室内で繁殖して大変な思いをされた飼い主さまも多くいらっしゃいます。
予防する期間は、お住まいの地域にもよりますが少なくとも4~11月くらいまでは予防することをおすすめします。
今は、3ヶ月に1回皮膚に滴下するだけのお薬もあるので、かかりつけの動物病院で相談して愛猫に合ったものを選んでもらいましょう。
なお、お家での処置は嫌がってできない猫が多いため、足裏のタフトを刈る場合や毛玉が出来てしまった場合は無理をしないで動物病院やトリミングサロンなどに依頼することをおすすめします。
メインクーンは身体が大きくなる猫種なので、飼育環境は広い場所が必要です。
トイレや食器、ケージなども体格に合わせて大きなものを用意し、キャットタワーなどの遊具はしっかりした造りのものを選ぶ必要があります。
また、メインクーンは水を怖がらない個体も多く、興味本位からお風呂や水槽に飛び込んでしまう場合もあるので、蓋をする等事故が起こらない様に十分注意しましょう。
遊び好きで知能が高いメインクーンにおすすめの運動メニューは、部屋のあちこちにフードやおやつを隠して探させる「宝探し」です。
はじめは猫のすぐ近くにフードをおいて探させることからスタートします。
見つけるのが難しいとかえってストレスが溜まってしまうので、最初は猫が簡単に見つけられる場所からはじめるなど、飽きずに遊べるように工夫してみましょう。
宝探しで家の中を歩き回ることは、「自分のテリトリーをチェックする」という猫の習性に沿ったものなので猫にとっても充実感があり、おすすめの遊びです。
ただし、猫によって遊びの好みが異なるので、床や壁に照射した光を追わせるLEDポインターや知育トイなど色々なものを試してみることをおすすめします。
わたしの勤務先に来院されている大型種の猫の飼い主さまに伺ったところ、上下運動よりも丸めた紙のボールをひたすら追いかけて平面で遊ぶ方が好きだと教えて下さいました。
このように猫が自ら好んで楽しく運動できるような遊び方は、猫のストレス解消と肥満防止の両方の効果があります。
なお、関節異常の有無に関わらず、猫が自ら動く場合を除いて、猫がピョンピョン飛び跳ねるような強い衝撃を繰り返し行う遊びは避けるべきです。
関節を痛めない運動方法で色々試して、ご自身の愛猫が好きな遊びを見つけてあげましょう。
メインクーンは、肥大型心筋症や多発性嚢胞腎、脊髄性筋委縮症、股異形成など遺伝性疾患が多い品種です。
上記の疾患は、病態によって猫の生活の質が著しく下がってしまうケースも考えられます。
普段から愛猫の様子をよく観察し、いつもと様子が違うと感じたらはやめに動物病院に連れていくことが病気の早期発見につながります。
その結果、完治できない病気であっても早期に治療をスタートすることで、愛猫が快適で長生きする可能性があります。
*注)脊髄性筋萎縮症はメインクーンにみられる遺伝性疾患で、有効な治療法はありません。
生後3~4ヶ月で発症し、四肢の筋肉が弱くなり萎縮(特に後肢の症状が重度)し、後肢の不全麻痺が進行する病気です。
筋肉の虚弱の程度は症例によって様々で、四肢で歩行可能な症例もいます。
子猫の頃からの習慣にしていただきたいのが歯磨きなどのデンタルケアです。
嫌がる猫が多いためか、歯磨きを実際に行っている飼い主さまは少なく、歯周病の猫が増えています。
最近では、わたしの勤務先でもほぼ毎週猫の歯科処置を行っています。
歯科疾患が重度であればあるほど腎臓病になるまでの日数が短いというデータがあるとおり、健康を保つためも歯のケアは非常に大切です。
歯のケアのコツは、いきなり歯ブラシを口の中に入れるのではなく、犬歯など磨きやすいところからスタートして、少しずつ慣らしていくことです。
お手入れの際には、指を噛まれないように注意すると同時に、歯磨きシートの誤飲に気をつけましょう。
デンタルケアは、歯磨きシートや歯ブラシ等を使ってきれいにすることが最も効果的ですが、どうしても難しい場合は、わたしの勤務先でも使用している歯科のケアに特化したサプリメントがおすすめです。
プロバイオデンタル kinber
shop|プレミアモード公式通販サイト
人間と同様、猫にとっても肥満は万病のもとで、肥満によって糖尿病、脂肪肝、下部尿路疾患のリスクが高まることが知られています。
また、高齢の猫に多い関節症は骨と骨との間がすり減って関節が変形する病気ですが、年齢と並ぶ二大原因が肥満です。
大型種のメインクーンは体重が重いため、他の品種と比較すると関節への負担は大きいことが予想されます。
愛猫が歳を重ねても健やかに過ごせる様に、太らせないように気をつけましょう。
ペットには、人間の様な公的な健康保険制度はありません。そのため、動物病院での治療費の負担は全額自己負担です。
状況によっては手術や長期間の通院、治療が必要になる場合や、それに伴い
何かあった時のための備えとしてペットのためにご自身で備えるという方法もありますが、突然のケガや病気など予想もしなかった事態に備えておくための選択肢の一つとして、ペット保険があります。
ペット保険とは、保険料をペット保険会社に支払うことで、飼い主が動物病院に支払う医療費の一部をペット保険会社が補償してくれるサービスです。
現在多くのペット保険会社がありますが、保険会社や契約プランにより、保険料や補償の内容等は異なります。
また、自分とペットにあった保険を選ぶには、情報を集めて比較検討をすることが大切です。
どんな補償内容が必要かは人によって異なりますが、ここではペット保険の選び方のポイントについてお伝えします。
ペット保険を選ぶポイントは以下の3つです。
補償内容が多ければ多いほど、さらにペットの年齢に比例して保険料は高くなり、実際に支払う保険料は、月額500円~1万円くらいまでとかなり差があります。
どの補償内容が必要なのか検討し、保険料とのバランスを考えて決めましょう。
補償内容は、手術のみ補償するプラン、通院も含め手術や入院も補償するプランなどいろいろなプランがあり、補償割合も30%~90%などがあります。
メインクーンがなりやすい肥大型心筋症は、心エコー検査を始めレントゲン検査、血液検査など定期的な検査を行い、病態に応じた内服薬の投薬を長期間内服する必要があります。
保険料とのバランスもありますが、「万が一の事態に備え高額になりがちなペットの治療費の負担を軽くし、さらに通院のハードルが下がる」という意味では通院と手術・入院を補償するプランがおすすめです。
ペット保険はペットの年齢が高ければ高いほど保険料が高くなるのが一般的で、ある程度の年齢になると加入できないプランもあります。
反対に、シニア専用の保険やシニアになっても継続できるペット保険もあります。
前述したとおりメインクーンの平均寿命は13歳なので、シニアになっても使えるペット保険に加入することをおすすめします。
保険会社によっては動物病院での支払い時に補償額を差し引いて窓口精算できる(対応可能動物病院のみ)ペット保険もあります。
医療やしつけについて獣医師に24時間無料電話相談ができるサービスが付帯しているペット保険もあり、初めて猫を飼う方には、この様な相談ができる付帯サービスがあるペット保険がおすすめです。
なお、ペット保険は病気やケガのために備える目的のものなので、ワクチンや不妊・去勢手術、ノミ・マダニなどの予防に関するものや保険加入前に発症している病気や先天性疾患に関しては補償の対象外なので注意しましょう。
ペット保険の補償には限度額や限度日数・回数など制限があるので、保険料や補償内容・年齢などの加入条件と併せて確認しておくと安心です。
この記事の監修者

現在複数の動物病院で臨床獣医師として勤務しながら専門知識や経験を活かして各種メディアや個人サイトでライターとして情報を発信している。
▼ドリトルけいのいぬねこ健康相談室
https://www.dolittlekei.com/
ライフワークは「ペットと飼い主様がより元気で幸せに過ごすお手伝いをする」こと。
取扱い保険会社・少額短期保険業者一覧