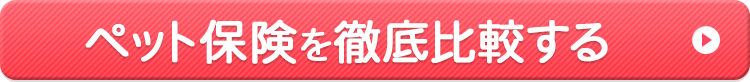ペルシャは、全身を覆うふわふわとした柔らかい被毛が特徴の猫種です。
正確なルーツは分かっていないものの、その美しい容姿から古くからショーキャットとして高い人気があり、現在では世界中で愛されています。
別名を「猫の王様」とも呼ばれており、映画などに登場することも珍しくありません。
現在ペルシャを飼育している、あるいは飼育を検討しているという方は多いのではないでしょうか。
そして、猫を飼うときに考えなければいけないことの1つがペット保険に加入するかどうかです。
ここではペルシャに多い病気についてご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
猫は猫種によってそれぞれ特徴があり、なりやすい病気も異なります。
ここでは、ペルシャの特徴と遺伝性疾患についてみていきましょう。
ペルシャが入れるペット保険を比較する
身体的特徴
まずは、ペルシャの身体的特徴についてご紹介します。
身体的特徴や性格を理解したうえで飼育を行うことで、病気になるリスクを低減することができますよ。
運動が苦手
ペルシャは運動があまり好きではなく、長時間遊んだり活発に動き回ったりすることはほとんどありません。
お気に入りの場所で、ゴロゴロと過ごすことを好みます。
ペルシャを飼うときには、この性格も踏まえたうえで健康管理を行う必要があります。
被毛の量が多い
見た目から分かる通り、ペルシャは被毛の量が非常に多く、身体だけではなく顔にもたっぷりと被毛が生えています。
ペルシャの最大の魅力ともいえる被毛ですが、健康を保つために被毛のケアが欠かせないことは頭に入れておく必要があります。
臆病な性格
高貴な印象のあるペルシャですが、性格は大人しくて従順、温厚です。
臆病な面があるので、強く叱ったりすると怯えてストレスを溜めてしまいます。
ペルシャには、どんなときでも優しく接してあげるようにしましょう。
遺伝性疾患
純血種は近親交配で生まれる個体が多いことから、遺伝性疾患を持っていることが少なくありません。
ここでは、ペルシャに多い遺伝性疾患をご紹介します。
多発性嚢胞腎
多発性嚢胞腎は優性遺伝の病気で、両親のいずれかが発症していると約50%の確率で発祥すると言われています。
多発性嚢胞腎になると腎臓にできた嚢胞が少しずつ大きくなり、腎臓が膨張していきます。
その後、最悪の場合は死に至ります。非常に怖い病気ですが、長期間無症状のことも少なくありません。
高齢になり、腎不全の状態になってから発見されることも多いようです。
尿路疾患
ペルシャは尿中にシュウ酸カルシウムという結晶ができやすいと言われており、これが膀胱内で大きな結石になることにより頻尿、排尿障害、血尿などの症状が出始めます。
また、小さな結石でも症状が出ることはあります。
早期発見できずに治療が遅れると尿毒症や急性腎不全になる可能性があるので、十分に注意しなければいけません。
眼瞼内反症
眼瞼内反症は、まぶたのフチが内側にめくれることによってまつ毛が目にあたってしまう病気です。
症状としては、目に痛みが生じる、目に傷ができる、などがあります。
症状が進行した場合には、手術をする必要があります。
毛球症
ペルシャはきれい好きな長毛種のため、グルーミングのときに多くの毛を飲み込んでしまうことが少なくありません。
その毛が胃や腸の中で塊になると、毛球症になります。
軽度であれば無症状ですが、限界量を超えると食欲不振や吐き気、嘔吐などの症状が出てきます。
さらに腸閉塞が起こる可能性もあるので、事前の予防が大切です。
皮膚病
長毛種がゆえに発生頻度が高いのが、皮膚病です。
ペルシャは毛が長く皮膚が見えにくいため、皮膚病になってもなかなか気付けないことがあるので注意が必要です。
たかが皮膚病と思ってしまいがちですが、悪化すると膿ができるなどして治療に時間がかかることがあります。
普段からのケアと、早期発見の心掛けが大切だといえるでしょう。
肥大型心筋症
肥大型心筋症は心筋症の中でも最も多いタイプの疾患で、左心室の心筋が肥大することによって起こります。
始めのうちは無症状ですが、重症化すると元気がなくなる、食欲がなくなる、呼吸が早くなる、舌が青紫色になるなどの症状が出てきます。
症状が出てからの平均生存期間は決して長くないため、できるだけ早期発見して対処する必要があります。
流涙症
流涙症とは、目から涙が溢れ出てしまう病気です。
原因は涙の排泄異常と涙の増加の2種類に分けられ、ペルシャをはじめとした短頭種で発症しやすいと言われています。
命にかかわる病気ではないものの、放置していると皮膚が炎症を起こしたり猫が目に不快感を感じたりするため、できるだけ早めの治療がおすすめです。
潰瘍性口内炎
潰瘍性口内炎とは、歯茎や頬の内側などに潰瘍ができる病気です。
猫の潰瘍性口内炎では非常に治りにくい重度な炎症が起こるため、軽視はできません。
症状としては、よだれが増加する、口の周囲が汚れる、口臭が強くなる、食事のときに痛みで悲鳴をあげる、食事を拒否する、などがあります。
また、強い痛みによって凶暴な性格になることもあります。
愛猫が病気になったときに治療するのが大切なのはもちろんのことですが、普段から病気の予防を心掛けることはもっと重要です。
ここでは、ペルシャを飼育するときに気を付けたいことについてご紹介します。
飼育時に気をつける事
まずは、ペルシャを飼育するときの基本的な注意点についてみていきましょう。
丁寧に毛のケアを行う
ペルシャといえば、ふわふわの毛が印象的ですよね。
しかし、皮膚病や毛球症を予防するためには丁寧なブラッシングが欠かせません。
スリッカーブラシやコームを使い、毎日ブラッシングを行いましょう。
また、シャンプーも定期的に行うことをおすすめします。
定期健診を受けさせる
ペルシャはなりやすい病気が多く、特に肥大性心筋症は早期発見が重要です。
しかし、一般的に発症してからはっきりと症状が出るまでには時間がかかります。
定期健診を受けさせて、病気の早期発見に努めましょう。
夏場は温度管理を徹底する
ペルシャは、あまり暑さには強くありません。
蒸し暑い夏場には、体調を崩してしまうこともあります。
暑い日には必ずエアコンを使用し、室内の温度管理を行うようにしてください。
生活面の注意点
ここでは、運動量や食事などに関する注意点についてご紹介します。
落ち着いた環境を用意する
ペルシャはのんびりとした猫種のため、たくさん運動できる環境を用意する必要はありません。
それよりも、落ち着ける環境を用意してあげることのほうが大切です。
騒がしい雰囲気は好きではないので、家に人を呼ぶときには特に気を遣ってあげてください。
食事管理をしっかりと行う
ペルシャは運動量が多くない猫種で、遊んでいてもすぐに休憩する子が少なくありません。
そのため、肥満にならないように食事管理をしっかりと行う必要があります。
低脂肪・高タンパク質のフードを、量を調節しながら与えるようにしましょう。
ここでは、ペルシャがかかりやすい多発性嚢胞腎、尿路疾患、眼瞼内反症、毛球症、皮膚病の症状、治療費用の目安についてまとめました。
ペルシャが入れるペット保険を比較する
| かかりやすい病気 |
主な症状 |
治療費用 |
| 多発性嚢胞腎 |
・水を飲む量が増える
・おしっこの量が増える
・長い時間おしっこをする
・口臭が強くなる
・元気がなくなる
・体重が減る
・脱水、便秘、嘔吐 |
45,000円 |
| 尿路疾患 |
・トイレに行く回数が増える
・おしっこが少ししか出ない
・おしっこをするときに痛がる
・血尿が出る
・おしっこが濁る
・粗相をする
・落ち着きがなくなる |
200,000円 |
| 眼瞼内反症 |
・まばたきの回数が増える
・涙の量が増える
・まぶたがピクピクと痙攣する
・結膜が充血する
・しきりに目をこする |
30,000円 |
| 毛球症 |
・食欲がなくなる
・吐き気を催す
・下痢をする
・腹部を痛がる
・発熱する
・元気がなくなる |
10,000円 |
| 皮膚病 |
・毛が抜ける
・かさぶたができる
・毛が脂っぽくなる
・かゆがる
・発疹が出る |
5,000円 |
なりやすい病気は、年齢によってもことなります。
愛猫の年齢でどのような病気になりやすいのかを把握しておくと、正しい対策が取りやすいといえるでしょう。
子猫~成猫
ペルシャが若いうちに注意したい病気としては、尿石症や流涙症があります。
また、短頭種気道症候群になることもあります。
これはマズルの短い短頭種に特有の病気で、パンティングや嚥下障害などの症状がみられます。
成猫~
加齢がリスクファクターになる病気としては、肥大型心筋症や多発性嚢胞腎などがあります。
他の猫種と同様に慢性腎臓病になる可能性も高く、水をたくさん飲む、おしっこが薄くなり量が増える、食欲がなくなるなどの症状が生じます。
ここでご紹介したように、ペルシャは様々な病気になるリスクを抱えており、治療することになった場合にはかなりの費用がかかります。しかし、ペット保険に加入していれば万が一のときも安心です。ここでは、ペット保険を選ぶときのポイントをご紹介します。
保険選びのポイント
ペット保険を選ぶときにまず重視したいのは、補償内容です。
猫種や年齢、現在の健康状態などによって、かかりやすい病気やリスクの高さは異なります。
愛猫がどのような病気になりやすいかを把握したうえで、それらの病気をカバーしているペット保険を選ぶといいでしょう。
また、優先順位をはっきりさせておくことも大切です。
ペット保険には色々な種類があり、それぞれ補償範囲や補償割合、保険料、更新年齢の制限、支払限度日数、特約、付帯サービスなどが異なります。
始めに優先順位をはっきりさせたうえで各ペット保険を比較し、どれに加入するかを決めるようにしてください。
保険料、補償内容の比較表
ペルシャが入れるペット保険を比較する