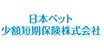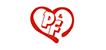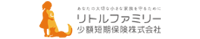【獣医師監修】
ミヌエットに多い病気やケガは?
ペット保険加入の必要性

ミヌエットという猫種を聞きなれない方もいらっしゃるかも知れません。ミヌエットとはペルシャとマンチカンの交配種で、やわらかく密な被毛と短めの四肢が特徴のアメリカ原産の猫種です。ブリーディングが始まったのは1995年、世界最大と言われるアメリカの猫種登録機関TICA(The International Cat Association)に公認されたのは2016年と比較的歴史が浅い猫種ですが、日本では人気が高く飼育頭数が増えています。
しかし、ペルシャとマンチカンの交配種であるが故に、この2つの猫種の好発性疾患が気になる猫種でもあります。 この記事によりミヌエットに多い病気について知って頂き、病気の予防や早期発見にお役に立てれば幸いです。
ミヌエットは、ペルシャとマンチカンの両方の特徴を受け継いでいます。ここでは、ミヌエットの特徴と遺伝性疾患についてお伝えします。
身体的特徴
<四肢が短め>
ミヌエットは、マンチカンから受け継いだ四肢が短いという特徴を持っています。ただし、マンチカンにも足が長めの個体がいるのと同様に、ミヌエットにも足が長い個体もいます。
<被毛・顔>
ペルシャ譲りの柔らかくフサフサの密な被毛が特徴で、短毛と長毛が存在します。また、被毛の色と毛のパターンは多種多様です。顔はペルシャよりも高めの鼻で、鼻の横もふっくらしています。
遺伝性疾患
<骨軟骨異形成症>
折れ耳のスコティッシュフォールドやマンチカンにもよくみられる遺伝性疾患で、骨の成長と関節軟骨の構造に異常が生じ、関節の可動域が狭くなる病気です。特に手根関節、足根関節、尾椎に強く症状がでて、痛みを伴うことがあります。
症状は、四肢の跛行や関節がコブの様に腫れるなど強い痛みある場合や、ちょっと動きが悪いくらいの軽度の症状しか出ない場合があります。治療方法は、痛みの緩和を目的に、サプリメントや鎮痛剤を投薬します。
<多発性嚢胞腎>
多発性嚢胞腎とは、腎臓内に嚢胞が多数形成される遺伝性疾患です。ペルシャ猫に多い遺伝性疾患で、両方の腎臓にできた嚢胞が、ゆっくりと数が増えて大きくなり、その結果正常な腎臓の細胞の組織が少なくなり、最終的には腎不全となり死に至ります。
ミヌエットの飼育時に気をつけたいポイントをまとめました。
飼育時に気をつける事
被毛が密で柔らかい毛質のため、毛玉にならない様に毎日のブラッシングを習慣にしましょう。気を付けたいのは、毛玉をハサミで切ろうとして皮膚をバッサリ切ってしまうことです毛玉が出来ない様に日々お手入れをすることが大切ですが、もし毛玉が出来てしまった場合は無理をせず動物病院やトリミングサロンなどに相談しましょう。
生活面の注意点
ミヌエットは、比較的おとなしい性格です。しかし、エネルギッシュな一面もあると言われています。マンチカンは活発で社交的、ペルシャは激しい運動は好まないためどちらの特徴が現れるのかは不明ですが、運動量が多い場合のことも考えてゆったりとした環境がおすすめです。
また、他の猫種と同様に肥満には注意が必要です。特にオスで肥満傾向がある場合は尿路結石ができるリスクが高くなるので、食事はミネラル分や脂肪分、カロリーの少ないものを与えましょう。
ミヌエットがかかりやすい病気は消化器疾患、下部尿路疾患、肥大型心筋症があります。それぞれ主な症状と治療費の目安を表にまとめました。
なお、動物病院によって治療費の設定が異なるので、治療費については一例としてお考え下さい。
| 主な症状 | 治療費の一例 | |
|---|---|---|
| 消化器疾患 | 食欲不振 元気の消失 腹痛 下痢 嘔吐 |
検便:1,000円~2,000円~ 血液検査:10,000円~ 皮下注射(下痢止め等):2,000円~ 皮下点滴:1,500円~3,000円 抗生剤・消炎剤投薬(7日分):内服薬1,500円~3,000円 |
| 下部尿路疾患 | トイレに頻繁にいく トイレの中に座っている時間が長い 陰部を頻繁に舐めている 痛がって鳴く 尿が出ていない |
尿検査:1,000円~4,000円 血液検査:10,000円~ レントゲン検査: 1枚5,000円~6,000円 エコー検査:5,000円~6,000円 抗生剤・消炎剤投薬(7日分):内服薬1,500円~3,000円 尿道カテーテル留置:3,000円~ |
| 肥大型心筋症 |
食欲低下 |
レントゲン検査: |
ミヌエットがかかりやすい病気を年齢別にまとめました。
子猫期(0~1歳)
<上部気道感染症(猫風邪)>
母猫からの移行抗体が減少してくる生後2か月前後にかかりやすい病気で、くしゃみ、鼻水、発熱、目やになど人間の風邪の様な症状が見られます。
原因はヘルペスウイルス、カリシウイルス、クラミジアなどの感染です。治療は点眼薬や点鼻薬、インターフェロンの投与などを行います。一旦症状がおさまっても再発する場合や、流涙や鼻づまりなどの症状が治らないケースもあります。
<消化器疾患>
消化器疾患とは食道や胃、腸など消化器系の病気のことです。この時期に特に多いのは下痢や嘔吐、そして異物誤飲です。特に飼い始めたばかりの子猫の時期は、環境の変化によるストレスや、寄生虫の感染などによる下痢が多く見られます。
また、異物の誤飲を防ぐためには、誤飲しそうなおもちゃなどを置きっぱなしにしないことが一番の対策です。いたずら好きな猫の場合には、留守番はケージに入れる様にする等工夫しましょう。
<猫伝染性腹膜炎>
猫伝染性腹膜炎は1歳未満のオスの子猫に発症しやすいと言われています。ある統計では、理由は不明ですが雑種より純血種での発生が多いという結果で、わたしの臨床経験上でも同じように純血種の猫に多い印象があります。猫伝染性腹膜炎ウイルスは、ほとんどのイエネコが感染していると言われる猫腸コロナウイルスが突然変異してできたと言われています。
症状は食欲元気の低下、発熱、体重減少が見られ、腹水や胸水が貯まるウエットタイプとブドウ膜炎、肝臓や腎機能が低下し神経症状がみられるドライタイプの二つのタイプがあります。この病気は、どちらのタイプも非常に治療の反応が悪く、残念なことに予後不良の場合がほとんどです。
成猫期(1歳~7歳)
<外耳炎>
外耳炎は猫には比較的多い疾患です。 原因はマラセチア菌という常在菌の増殖や細菌感染、耳ダニなどの外部寄生虫、過剰な耳のケアなど様々です。治療は点耳薬や駆虫薬など原因に合わせた治療を行います。
<下部尿路疾患>
下部尿路疾患とは、膀胱と尿道の病気のことで、特に多いのは特発性膀胱炎です。しかし、下部尿路疾患は、尿石症や尿路感染症、腫瘍などが原因であっても頻尿や排尿困難、血尿などの同じような症状がみられるので、何が原因なのかを調べることが大切です。
また、尿道が閉塞している場合は、命に関わるのでなるべく早く治療する必要があります。最近は自動トイレやシステムトイレを使っている方が増えていますが、愛猫がきちんと排尿しているかどうか毎日確認しましょう。
シニア期(7歳~)
<慢性腎臓病>
シニア期の猫が最もかかりやすい病気の一つです。症状は多飲多尿、食欲不振、毛並みが悪くなる、痩せてくるなどで、この様な症状が見られた時には腎臓の機能の7割近くがダメージを受けている状況です。
そして、壊れてしまった腎臓の細胞は元通りに再生させることはできません。治療は、内服薬の投薬や食餌療法、輸液療法などで、残った腎臓の機能をなるべく良い状態に維持することを目的として行います。
<甲状腺機能亢進症>
シニア期の猫に多い内分泌疾患です。原因は、甲状腺過形成、甲状腺濾胞腺腫、甲状腺癌で、甲状腺の機能が亢進しすぎることで、異常に食欲が旺盛になり、その割には体重が減少していきます。鳴き声が大きくなる、昼夜に関わらず良く鳴くなどの症状が見られたらこの病気を疑います。
診断は、触診や血液検査を行い、甲状腺ホルモンの値を確認します。治療は、食事療法や甲状腺の働きを止める内服薬の投薬を行う内科療法か、甲状腺の摘出手術を行う外科療法を行います。
ペットには、人間の様な公的な健康保険制度はありません。そのため、動物病院での治療費の負担は全額自己負担です。状況によっては手術や長期間の通院、治療が必要になる場合や、それに伴いペットの医療費も高額になる可能性があります。
何かあった時のための備えとしてペットのためにご自身で備えるという方法もありますが、突然のケガや病気など予想もしなかった事態に備えておくための選択肢の一つとして、ペット保険があります。
ペット保険とは、保険料をペット保険会社に支払うことで、飼い主が動物病院に支払う医療費の一部をペット保険会社が補償してくれるサービスです。現在多くのペット保険会社がありますが、保険会社や契約プランにより、保険料や補償の内容等は異なります。どんな補償内容が必要かは人によって異なりますが、ここではペット保険の選び方のポイントについてお伝えします。
ペット保険選びのポイント
ペット保険を選ぶにあたって優先順位が高いのは、
- ●保険会社に支払う保険料
- ●加入時の年齢
- ●補償内容
の3つだと思います。
保険会社に支払う保険料について
保険料は最も安いものでは月に500円~、金額が多いプランでは1万円前後です。補償内容が多ければそれに伴って保険料も高くなるので、情報を集めて比較検討する必要があります。
また、保険会社や加入プランによって異なりますが、加入してから終身までずっと同じ保険料ではなく、保険料の見直しがあるのが一般的です。若い時は安い保険料でも更新の度に保険料が上昇するプランや、ある程度の年齢になったら保険料が一定になるプランなど色々なプランがあります。
加入時の年齢
ペット保険は、ペットの年齢が高ければ高いほど保険料が高くなるのが一般的で、ある程度の年齢になると加入できないプランもあります。 猫の平均年齢を考えると、シニアになっても継続できるペット保険を選択することをおすすめします。
保険会社によっては動物病院での支払い時に補償額を差し引いて窓口精算できる(対応可能動物病院のみ)ペット保険や、医療やしつけについて獣医師に24時間無料電話相談ができるサービスが付帯しているペット保険もあります。特に初めて猫を飼う方には、このような治療費の補償以外の付帯サービスがあるとより安心です。
なお、年齢が上がるにつれて保険料が高くなり加入条件が厳しくなるのが一般的で、プランによっては加入できなくなる場合もあります。最近ではシニア用(8歳~)のペット保険も増えていますので、将来のことも考えて情報を集めておくと安心ですね。
補償内容について
補償内容は保険会社やプランによって様々で、
- ・病気やケガによる通院や入院を含め手術もすべて補償する
- ・手術に関する治療費のみ補償する
- ・保険会社が補償する割合は30%、50%、70%が多い(90%や100%もある)
- ・1回の手術につき50万円を補償するなど手術に特化している
などがあります。
補償内容を選ぶポイントとしては、外耳炎など何度も通院が必要になる場合も考慮すると同時に、尿路結石などの手術が必要になるケースを考えて通院治療だけでなく手術の補償も網羅するプランが安心です。
なお、ペット保険は「病気やケガに備える」という目的のものなので、不妊去勢手術、ワクチン接種やノミ・ダニ予防など予防に関するものや、保険加入以前にかかっていた病気やケガについては補償対象外です。
また、保険会社やプランによっては、先天性疾患の補償をしないケースもあります。ミヌエットの品種好発性疾患や遺伝性疾患が補償の対象であるか、保険の加入前に確認しておくことも大切です。
なお、保険会社による補償は無制限ではなく上限(支払限度額または支払限度日数・回数)があります。補償内容をしっかり確認してご自身と愛猫にとって必要なプランを選びましょう。
この記事の監修者

現在複数の動物病院で臨床獣医師として勤務しながら専門知識や経験を活かして各種メディアや個人サイトでライターとして情報を発信している。
▼ドリトルけいのいぬねこ健康相談室
https://www.dolittlekei.com/
ライフワークは「ペットと飼い主様がより元気で幸せに過ごすお手伝いをする」こと。
取扱い保険会社・少額短期保険業者一覧